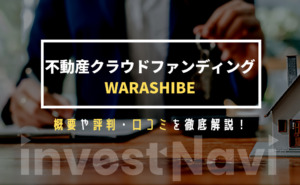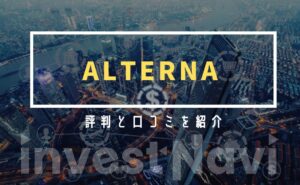ソーシャルレンディングの税金とは?税制度や節税方法を徹底解説!
今回は、ソーシャルレンディングの税金制度や節税方法、確定申告の注意点について詳しく解説していきます。
ソーシャルレンディングは、株式や債券、仮想通貨など他の投資と同様に税金がかかります。
具体的にかかる税金、節税の方法など、より効率的にソーシャルレンディングで投資を行うことができる方法ついて説明していきたいと思います。
ソーシャルレンディングでの税金について気になる方、ソーシャルレンディングでの投資を考えている方は、是非この記事を参考にしてみてください。
・20.42%が源泉税として控除済み
・所得税を実際の計算例を用いて解説
・ソーシャルレンディング で節税方法は大きく4つ
・ソーシャルレンディングでの収益は「雑所得」として分類される
ソーシャルレンディングを始めてみたいという方には、バンカーズがおすすめです。

バンカーズは比較的新しいソーシャルレンディングサービスですが、今物凄い勢いで伸びており今後注目されることが間違いないサービスだと言われています。
投資自体は1万円と少額から始めることができ、 多くの資産を所有していなくても、投資を始めることができる点が最大の魅力です。
今なら会員登録とメルマガ登録でもれなく2000円分のAmazonギフト券がもらえるキャンペーンを行っています。
この機会を逃さずに登録しておきましょう。
ソーシャルレンディングにおける税金のポイント
ソーシャルレンディングにおける税金のポイントは以下の3つです。
・収益の20.24%が源泉税として控除済
・所得は「雑所得」として分類
・納税が源泉徴収のみではない
収益の20.42%が源泉税として控除済み
ソーシャルレンディングだけではなく、株式や債券などへの投資による収益には、税金が発生します。
ソーシャルレンディングでは、自身が投資した額に対して、利率分を掛け合わせたものが配当金として口座に送金されます。
収益(配当金)は、ソーシャルレンディングサービス会社から税金分が控除された状態で口座に送金されているので、実質、すでに税金を支払っていると言えます。
上記のような仕組みを「源泉徴収」と呼び、聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
ソーシャルレンディングでの配当金にかかる税率は一律20%であり、そこに0.42%の復興特別所得税が加算され、合計20.42%の税金が支払われる前にすでに差し引かれています。
ソーシャルレンディングでの所得は「雑所得」として分類
会社に勤めている方が毎月支払われる給料であれば給与所得、株を所有している方が得る配当金は利子所得など、世の中のあらゆる所得は、種類によって分類されています。
そして、ソーシャルレンディングにおける収益の場合は「雑所得」として分類されることとなります。
雑所得は、日本で存在している10種類の所得の中で、どれにも当てはまることのない所得のことを指しているのです。
| 利子所得 | 債券・預貯金等の利子 |
| 配当所得 | 株式配当や出資による配当 |
| 不動産所得 | 家賃・土地代など |
| 事業所得 | 事業をしている場合に発生する所得 |
| 給与所得 | 会社からの給料など |
| 退職所得 | 退職金など |
| 山林所得 | 山林を売却した際に発生する所得 |
| 譲渡所得 | 財産(土地など)を売却した際に発生する所得 |
| 一時所得 | クイズや懸賞金などによって発生する所得 |
| 雑所得 | ソーシャルレンディングでの収益など、上記に当てはまらない所得 |
雑所得に当てはまる所得の他の例としては、FXやアフィリエイトで得た収益などです。
また、雑所得とはいえ、得た利益は所得であることには変わりないため、他の事業で得た収益と合算して確定申告を行う必要があります。
ソーシャルレンディングに関する確定申告の詳しい情報については後述していきます。
納税は源泉徴収のみではない
前述している通り、ソーシャルレンディングで得た収益はあらかじめ20.42%が控除されています。
しかし、所得税には「総合課税方式」と「分離課税方式」の2つが存在しており、ソーシャルレンディングは総合課税方式に分類されます。
総合課税方式とは、自身が受け取った収入を全て合算した後に、基礎控除・配偶者控除などを行った金額に対して所得税を計算する方式です。
つまり、ソーシャルレンディングで得た利益はすでに源泉徴収されている状態ではありますが、収益を受け取る人間の所得状況などによって、所得税額は変動するということです。
ソーシャルレンディングにおける税金制度
ソーシャルレンディングで得た利益に対して発生する税金を把握するためには、税制度について理解しておく必要があります。
また、実際の所得税の計算例を用いてわかりやすく解説していきたいと思います。
所得税の税率
前述している通り、ソーシャルレンディングの利益は総合課税方式で所得税が計算されます。
そのため、自身の所得合計によって所得税は変動することとなります。
所得税の税率は最低5%〜最大45%の割合で所得に対して課税され、実際に発生する所得税は以下の通りです。
| 課税対象所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
実際の所得税の計算例
上記にて紹介している、所得税の税率を用いて、実際に発生する所得税の計算を行っていきます。
例えば、年収300万円のサラリーマンの方がソーシャルレンディングを利用して、年間20万円の収益を得た場合、年間合計所得は以下の通りです。
給与所得300万円+雑所得20万円=320万円
所得税率の表を確認してみると、年間合計所得が320万円の方であれば、「195万円~330万円未満」に該当します。
そのため、「税率:10%」かつ「控除額:97,500円」となります。
計算してみると、320万円×10%ー97,500円=222,500円 が所得税となるのです。
ソーシャルレンディングでの節税方法
ソーシャルレンディングで得た利益を節税する方法は大きく分けて以下の4つです。
・夫婦において所得が低い方の名義で投資をする
・経費として申告する
・法人を設立する
・確定申告による税金の還付を受ける
夫婦において所得が低い方の名義で投資をする
総合課税は、合算して計算されるため、夫婦において所得が低い方の名義で投資を行った方が節税効果が見込めます。
例えば、年収600万円の夫がソーシャルレンディングで50万円利益を得た場合、所得税率が20%で計算されるため、発生する所得税は10万円です。
しかし、年収100万円の妻がソーシャルレンディングで50万円利益を得た場合、所得税率が5%で計算されることとなります。
そのため、発生する所得税は25,000円だけです。
上記のような場合ですと、75,000円もの差額が生まれるため、節税効果の高いことが確認できます。
経費として申告する
自身がソーシャルレンディングを行うにあたって発生した費用を経費として申告することで、節税が可能です。
所得とは経費を引いた金額のことを指しているため、経費がかかればかかるほど所得を抑えられます。
しかし、ソーシャルレンディングに関わる経費として計上できるのは以下のような費用だけです。
・入出金手数料
・インターネット通信費(全額では無い)
そのため、当然配当金を経費として計上することはできませんし、経費計上のためには証明としてレシート・領収書が必要となりますので、必ず保管しておきましょう。
法人を設立する
自身の年間所得が900万円以上であれば、法人を設立することで節税効果が見込めます。(年間所得が900万円以上で所得税率が33%となるため。)
個人での所得税計算では、最大45%税金として発生してしまいますが、法人の場合一定以内の利益であれば最大でも20〜25%前後しか所得税が発生しません。
そのため、配当金が増幅している方であれば、法人を設立することをおすすめします。
確定申告によって税金の還付を受ける
年間の所得が330万円以下の方であれば、確定申告することで税金の還付を受けることが可能です。
確定申告とは、1月1日から12月31日まで1年間の所得を国に報告し、納税することを指しています。
年間の所得が330万円以下の場合、源泉徴収分の20.42%から所得税額の10%を差し引いた、10.42%が返還されます。
これは、所得額が195万円〜330万円未満であれば所得税率は10%であるのにも関わらず、配当金から20.42%、つまり10.42%分が余分に税金として控除されてしまっています。
確定申告によって、この余分に徴収されてしまった10.42%分の税金の還付を受けることができるイメージです。
ソーシャルレンディングで節税する際の注意点
ソーシャルレンディングでは、上記4つの方法で節税が可能です。
しかし、節税を行う際は以下の2つのポイントについて注意が必要です。
繰越控除を行うことはできない
損益通算を行うことができない
繰越控除を行うことできない
ソーシャルレンディングでの損失分は、繰越控除を行うことができません。
繰越控除とは、本来行う予定であった控除を利益がマイナスになったことで受けられなくなってしまったとしても、翌年以降に繰り越して適用できる制度です。
例えば、株式の配当金などは、累計でマイナスになってしまったとしても、3年間は繰り越すことができます。
そのため、当該年がマイナスでもその翌年にプラスになれば、昨年も分も含めて控除ができるということです。
しかし、ソーシャルレンディングに関しては、繰越控除が適用できないため、通常通り税金を支払わなければなりません。
損益通算を行うことができない
ソーシャルレンディングの収益のマイナス分は損益通算できません。
損益通算とは、別々の種類で得た所得を相殺することを指しています。
例えば、変動なく受け取っている給与所得が年間300万円、配当所得が今年はマイナス50万の場合、300万円-50万円=250万円で所得計算を行います。
しかし、ソーシャルレンディングは、損益通算適応外となりますので、どれだけマイナスが出ても別所得に合算することはできません。
ソーシャルレンディングを初めてみたいという方にはバンカーズがおすすめです。
書類提出は全てオンラインで完結し、最短約8分で口座開設の申し込みが可能なので是非開設してみてください。
ソーシャルレンディングにおいての確定申告
続いては、ソーシャルレンディングで得た利益を確定申告する必要がある方や確定申告を行う流れについて解説していきます。
確定申告が求められる場合
確定申告が求められる人は、大きく分けて以下の3つです。
・会社員
・個人事業主
・扶養家族
会社員
会社員は、源泉徴収を行ってから給与所得が発生します。
また、確定申告に関しても「年末調整」といった形で、全て会社が行ってくれるため、会社員が行う必要はありません。
しかし、給与所得以外での収入に関しては、別途確定申告を行い納税する必要がありますが、20万円以下の収入であれば、確定申告を行う必要がなく、ソーシャルレンディングで得た利益に関しても適用されます。
20万円以上の利益である場合や給与所得が年間2000万円以上の場合は、給与所得以外の収益に関して、個別で確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。
個人事業主
個人事業主は、収益にかかわらず、自身で確定申告を行う必要があります。
また、ソーシャルレンディング以外の収益に関しても、申告する必要があるため、必ず確定申告が求められます。
扶養家族
結婚している場合、夫・妻は「基礎控除」と「給与所得控除」を適用させることが可能です。
基礎控除とは、所得が38万円以下であれば全額控除されるため、所得税が発生せず確定申告の必要がない控除のことを指します。
また、給与所得控除とは、給与所得を受け取っている方で、65万円以下であれば全額控除されるため、所得税が発生せず確定申告の必要がない控除のことを指します。
つまり、給与所得を受け取っていない方はソーシャルレンディングで38万円までであれば、利益を出しても申告の必要がありません。
確定申告を行う流れ
確定申告を行ったことのない方であれば、「難しい・書類がたくさん必要」など申告手続きに抵抗を感じている方も多いでしょう。
実際には、以下のような手順で確定申告は行なえます。
1.支払調書・医療費の明細書と病院等の領収書を保管
2.税務署もしくは国税庁のHPから申告書を受け取る
3.生年月日・収入・所得額を記載・入力
4.税務署に提出
医療費の明細書や病院等の領収書さえ用意していれば、確定申告は非常に簡単です。
国税庁のHPには、細かく申告書の記載方法が掲載されているため、悩むことなく作成できるでしょう。
住民税の申告は求められている
ソーシャルレンディングの収益は、所得税と復興特別所得税のみが控除されています。
そのため、住民税は控除されていないため、自身で市区町村へ申告する必要があります。
手続き方法や納付方法は市区町村によって異なるため、窓口で説明を受けることをおすすめします。
ソーシャルレンディングを始めるにはバンカーズがおすすめ

バンカーズは、2020年12月よりサービスを開始した、比較的新しいソーシャルレンディングサービス会社です。
バンカーズは、すでに累積募集金額が 28,566,820,000円に到達するなど、非常に将来が期待されている会社です。

また、上の画像のように1万円からの少額投資が可能ですので、少ない資本で手軽に投資でき、投資初心者の方にとってもおすすめできます。
また、最短約8分で口座開設の申し込みが可能であり、登録後最短3営業日から投資を始めることができます。
書類提出は全てオンラインで完結しますので、気になる方は是非バンカーズの公式サイトを確認してみてください。
ソーシャルレンディングの税金についてのまとめ
今回はソーシャルレンディングの税金制度や節税、確定申告の注意点を紹介していきました。
これから投資を始めたいと考えている方は、是非この記事の情報を参考に所得税を抑えて投資してみてください。
・総合課税方式を採用しているため、自身の所得額によって納税額は変動する
・節税するなら、夫婦所得が低い方の名義で投資を行い経費申告・法人の設立などがおすすめ
・住民では市区町村ごとに納税が必要
・ソーシャルレンディング始めるなら「バンカーズ」がおすすめ
ソーシャルレンディングを始めるには、バンカーズがおすすめです。
まだ口座をお持ちでない方は、是非口座を開設してみてください。